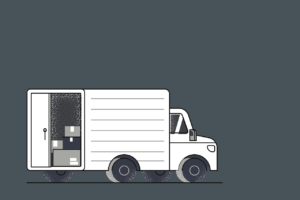「保育園と幼稚園ってどう違うの?」
「認定こども園って保育園の仲間?それとも幼稚園?」
同じように“子どもを預かる場”でも、制度や運営のしくみは大きく異なります。
とくに共働き家庭・シングル家庭では、
「預けられる時間」や「保育料の仕組み」が生活に直結するため、違いを正しく理解して選ぶことが大切です。
この記事では、保育園・幼稚園・認定こども園の制度上の違いを整理し、
働き方・預け時間・費用の視点から比較してわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 保育園・幼稚園・認定こども園の基本的な違い
- 1号・2号・3号認定の違いと対象世帯
- 預かり時間の違い
- 無償化制度の適用タイミング
- 入園前に確認しておきたいポイント
それぞれの役割と運営元の違い
まず、大きな違いは「目的」と「管轄」が異なる点にあります。
保育園
- 目的:保護者が働いているなど、家庭で保育できない場合に預かる施設
- 管轄:厚生労働省
- 必要条件:就労証明などが必要(原則 0歳~就学前まで)
幼稚園
- 目的:教育を行う学校(“幼児教育”がメイン)
- 管轄:文部科学省
- 必要条件:就労条件は不要(3歳~就学前)
認定こども園
- 目的:保育+幼児教育の両方を提供する施設
- 管轄:内閣府(厚生労働省、文部科学省)
- 利用区分によって保育園型/幼稚園型どちらにもなる
認定区分(1号・2号・3号)による違い
認定こども園と一部の幼稚園は、子どもの利用区分によって制度が変わります。
| 区分 | 対象 | 利用目的 |
|---|---|---|
| 1号認定 | 3〜5歳 | 教育利用。保育必要性は問わない |
| 2号認定 | 3〜5歳 | 就労などで保育が必要な家庭 |
| 3号認定 | 0〜2歳 | 就労などで保育が必要な家庭 |
※ 1号認定=幼稚園寄り
※ 2号・3号認定=保育園寄り
同じ「こども園」でも、区分によって預かり時間や費用が変わるため、入園前に必ず確認する必要があります。
預かり時間の違い
- 保育園:8〜11時間が基本(延長保育あり)
- 幼稚園:4〜5時間が標準(預かり保育あり/別料金)
- こども園:認定区分により保育園型 or 幼稚園型に近くなる
フルタイム勤務・シングル家庭の場合は「開園時間の長さ」が重要な選択軸になります。
無償化のタイミングの違い
- 保育園:0〜2歳は自己負担、3〜5歳は基本保育料が無償
- 幼稚園:満3歳の誕生日以降から教育費が無償(上限あり)
- こども園:認定区分ごとに異なる
※無償化されるのは「保育料・教育料のみ」であり、
給食費(主食/副食)、延長保育料、バス代、行事費などの多くは自己負担。
※ただし、運用ルールは自治体や園ごとに異なるため、事前に確認は必要です。

シングルマザーの視点で選ぶときに大切だったこと
働きながら子育てを続ける場合、園選びでは「生活が回るかどうか」が大きな判断材料になります。
とくに、延長保育・急な呼び出し・持ち物負担・行事の開催曜日などは入園後の負担を左右するポイントです。
私は園見学の段階でここを確認しておいたことで、入園後のミスマッチが防げました。
より具体的な質問リストは、こちらの記事にまとめています。

年間保育日数の違い|休園日の多さも大きな差になる
保育園・幼稚園・認定こども園は、年間の開園日(利用できる日数) にも違いがあります。
- 保育園(2・3号認定)
→ 開園日数は「年間約300日」
→ 園によって異なるが、日曜日や祝日、年末年始以外は利用できる - 幼稚園(1号認定)
→ 開園日数は「39週以上」
→ 基本的に「平日の週5日・春夏冬の長期休みあり」 - 認定こども園
→ 1号利用なら幼稚園と同じ、2・3号利用なら保育園と同じ
→ 「どの認定で利用するか」で年間利用日数が変わる
「保育できる日数・時間」にはかなり差があるため、働く家庭ほど注意が必要です。
まとめ
保育園・幼稚園・認定こども園は、対象年齢や保育時間、無償化の開始タイミングなどがそれぞれ異なります。
制度の違いだけで選ぶのではなく、家庭の働き方・預けたい時間・費用負担・園の方針との相性を含めて比較することが大切です。
とくに見落としやすいポイントは次の3つです。
- 無償化=完全無料ではない(給食費・預かり保育料などは自己負担)
- 同じこども園でも「認定区分」で制度が変わる
- 幼稚園は保育日数・預かり時間が短いことが多く、共働き家庭は追加料金が発生しやすい
園選びに正解はありませんが、
「どこなら安心して預けられるか」「無理なく続けられるか」を基準にすると、後悔しにくい選び方ができます。
入園前の見学や説明会は大きな判断材料になるため、気になる園があれば早めに情報収集しておくと安心です。